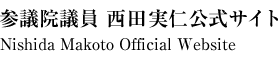213-参-総務委員会-005号 2024年03月22日
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
今日は、まず固定資産税等の過大徴収、いわゆる課税ミスについてお聞きをしたいと思います。
固定資産税は、言うまでもなく、市町村による行政サービスを提供する主たる税収であります。基幹税と言われておりまして、その税収に占める割合は約四割とされています。しかし、その基幹税と言われる固定資産税については、以前から過大徴収とかあるいは課税ミスの報道が相次いでおりまして、今日お配りをしました資料は、ここ数年の、まあ二、三年なんですけれども、過大徴収事案の一部についてまとめております。国会図書館のお力をお借りして、私の事務所で作成をしたものでございます。
ここ数年といっても二年余りなんですけれども、大きな額でいいますと、例えばA市におきましては、二〇一四年から二二年度の九年間で利息合わせて約一億円の還付ということが起きておりまして、その原因は県税事務所の担当者が誤った数値を使用していると、今後は再発防止として県が不動産評価した場合は市も確認をするというようなことも報道されておりましたし、また、B市におきましては、二つの法人が所有する建物について二十年間の過大徴収、利息合わせて四千五百三十一万円を還付したというような報道がございました。これはよくあるようでして、固定資産税台帳に鉄骨造を鉄骨鉄筋コンクリートと誤って登録をしたことが原因というふうにされております。また、D市を見ますと、三百四十一件、計一億一千八百三十万円を過大徴収していたということで、その原因は軽減の特例措置あるいは負担調整措置の適用漏れと、こういう適用漏れということもよくあるようでございます。
なぜこのような基幹税と言われる固定資産税に過大徴収が起きるのか。以前から様々指摘もされ、国会でも指摘されてきたと思いますけれども、やはり市町村の活動を支える基幹税たる固定資産税だけに、なおさら課題の解決が急がれるところではないかと思っております。
総務省でも、もちろん手をこまねいているばかりではございませんで、平成二十四年度、二〇一二年度に固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果を公表し、平成二十四年には、税額修正の主な原因や代表的な防止策に係る具体的な事例などをまとめて地方団体に周知をしておられます。また、平成二十六年には、納税者の信頼を確保するため、各市町村において課税事務の検証や固定資産評価員等の専門知識の向上、また納税者への情報開示の推進等を行うよう通知、助言を行っておられます。その上で、こうした再発防止策の周知を行った後の平成二十八年、二〇一六年には、フォローアップ的な意味を込めて再度調査を行っておられます。
しかし、こうした総務省によります通知あるいは助言にもかかわらず、税額修正した納税義務者数が一人以上あった市町村の比率というのは、調査回答団体のうち九割以上と言われている状況は残念ながら変わっていないということでございます。
その要因、原因ですね、これは時間がたってもほぼ同じであります。土地の税額修正の最大の要因は、やはり評価の誤り及び負担調整、特例等の適用誤りでありますし、家屋の間違いの多くは家屋滅失漏れとか新増築家屋額修正漏れといったものでございまして、いろいろ助言や通知を行っているんだけれども、そんなに変わっていないという現状であります。
じゃ、どうするのかということなんですけれども、基本的には、職員の方がもっと増えて実務研修を徹底的に行って、法律どおりに実地検査を行えば改善できるという意見もある一方で、抜本的な制度改革を求める意見もあるやに聞いております。
例えば、東京都の税制調査会では、もう随分古い、二十年ぐらい前の提言ですけれども、課税権と評価権を分離してはどうかとか、あるいは広域評価専門機関を設置してはどうかという提言もなされたようであります。
また、別の意見では、固定資産税を現行の賦課課税方式から申告納税方式に変えた方がいいんじゃないかとか、あるいは家屋の評価方式を再建築価格方式ではなくて取得原価方式にしてはどうかというような意見も出てございます。
実際に現場で担当されている方からは、人手不足でノウハウがなかなか継承できないという悲鳴のような声も上がっておりますし、複雑な仕組みのままでは今後もミスが続くんではないかということで、簡素で分かりやすい仕組みにどう見直すかというような指摘もあるようでして、私も税制に関わっている一人として耳が痛い話でもございます。
そういうわけで、こうした基幹税たる固定資産税の過大徴収、この現状への認識と今後の対策について、総務省並びに大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 委員おっしゃるとおり、固定資産税は市町村の基幹税でございますし、大変大切であるというふうに認識をしておりますが、固定資産税そのものの在り方については、また委員も今お話もありましたとおり、与党の税制調査会などでも様々御議論をいただくものではないかというふうに考えておりますが、課税誤りにつきましては、今これも御指摘をいただきましたが、総務省としても実態把握に努めてまいりました。
課税庁である市町村関係団体とも連携し、課税誤りの防止策に係る具体的事例を取りまとめるなど、その防止に向けた取組を進めてまいりました。毎年度、その当初に各市町村に対して大臣通知を発出し、納税者の信頼を確保するため、事務処理体制の整備や課税客体等の的確な把握を行い、課税誤りが生じることがないよう助言を行っております。
固定資産税におきましては地方団体の税務システムの標準化を進めておりまして、このような取組も課税誤りの防止につながるものではないかというふうに考えております。
今後も、機会を捉えて、課税誤り防止に向けて各市町村の取組を支援してまいりたいと考えております。
○西田実仁君 今大臣がお話しのように、この固定資産税も含めて、自治体の税務システムの標準化などを通じた税務手続のデジタル化ということで、徴税事務の効率化や適正化に取り組んでおられるというお話であります。また、標準仕様書の中でも、課税誤りを防止するためのエラーアラート機能、これの実装を必須としているというようなお話もお聞きをいたしました。
様々に工夫をいただいているわけですが、ここでは、地方税の、地方税統一QRコードの活用も含めたeLTAXの電子納付、この納付実績と今後の普及についてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
令和五年四月から、固定資産税、自動車税種別割等の四税目を必須といたしまして、地方税統一QRコード、いわゆるeL―QRと呼んでいるものでございますが、を活用いたしましたeLTAXにおける電子納付の仕組みが稼働したことによりまして、地方税収納におけるeLTAXの活用は拡大しております。
令和五年四月から十二月、まだこれ通年でございませんが、四月から十二月までの納付件数は約七千二百六十万件、これは、令和四年度の通年で一千二百万件だったものが七千二百六十万件に増えていると。納付額で見ましても、約十兆円と、これは、令和四年度の通年度で四・五兆円でございましたので、まだ十二月まででございますが倍以上に伸びていると、このような状況になっております。
今後も、この四税目以外の税目についても可能な限りこのeL―QRを活用するよう地方団体へ働きかけるなど、更なるeL―QRの普及に取り組みますとともに、eLTAXの利用件数や取扱金額、これが大きく伸びていることなどを踏まえまして、eLTAXの安定的な運用、納税者の利便性の向上、こういったことに努めてまいりたいと考えております。
○西田実仁君 是非、自治体における納付状況の管理が効率化されるように、更に促していただきたいと思います。
自治体による課税のめぐるトラブルは実はほかにもございまして、先日、地元のある社会福祉法人から、障害者相談支援事業に関する委託費について、消費税が含まれているかどうかで自治体との間で食い違いが生じ困っているとの御相談がございました。どうやら他の自治体でも同様の問題が生じているようで、報道によれば、消費税相当額の過去分の支払事例が相次いでいるというふうに報じられております。
この事業は、障害者やその家族からの相談に応じて福祉サービスの情報を提供するものでありまして、専門性が求められるために社会福祉法人に委託される市町村が多いと聞いております。
二〇〇六年の障害者自立支援法の施行によりまして、委託費は消費税の課税対象とされたにもかかわらず、障害者相談支援は非課税と自治体側が誤認し、混乱が生じているようです。厚労省からは既に昨年の十月に通達が発出をされ、同事業は消費税の課税対象であることが改めて周知徹底されたものの、課税対象であることはもっと以前から周知をしておくべきであり、また自治体側も関係法令の確認を十分にすべきであるというふうに思っております。
そもそも、委託する自治体側と受託する社会福祉法人の間で交わされる契約書に消費税の適用に関する記載がないのか。本来、普通、民民の取引ではあると思いますけれども、契約書に本来記載すべきではないかと考えますが、所管の厚労省にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。
市町村が実施をいたします障害者相談支援事業につきましては、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象となるところでございますが、この取扱いについて厚生労働省として明確に周知をしてこなかったところであり、誤認する自治体や事業者が一定数生じているものと認識をしております。
このため、昨年十月に発出した事務連絡において、障害者総合支援事業は消費税の課税対象であること、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があること、その旨委託先の事業者にも周知徹底いただきたいことなどについて自治体にお示しをし、本年二月の全国会議においても改めて徹底をしたところでございます。
各自治体と委託事業者の間で締結される契約に係る契約書における消費税に関する記載の要否については、制度として特に定めがあるものではなく、各自治体において判断されているものと承知をしておりますが、自治体及び事業者の双方が契約に当たっても消費税の取扱いについて誤認することがないということは大変重要なことでございます。このため、御指摘のように契約書に記載する方法も対応策の一つと考えておりまして、こうした対応を含めて各自治体には更に周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
○西田実仁君 書いていないことによって、これが内税なのか外税なのかということでトラブルになっているというのが現実でありますので、是非徹底をお願いしたいと思います。
全然別件ですが、先日、地元埼玉県西部地域の消防指令センター開所式というところに参加をさせていただきました。ここは西部地域の消防組合ほか構成四組合が消防指令業務を共同運用するためのセンターの設置です。この四月から業務を開始すると聞きました。
指令センター内も特別に視察をさせていただきました。迅速、円滑な指令管制と継続運用を実現するための指令システムでありまして、指令装置は通常四画面、フルタッチパネルディスプレーで構成され、電子ペンや手書き文字認識を採用することで操作性の向上が図られていることがよく分かりました。
中でも関心を持ったのが、Live119と言われるソフトでございました。これは民間の方が開発したものを採用しているということですが、スマホから一一九番通報時に、現場の状況を音声だけではなく映像も活用して通報が行えるシステムであります。全国でも同様のソフトが既に導入をされている地域が多いようでして、現場に向かう間に状況を把握しながら準備を整え、素早い救急活動に当たることができる優れたものだという印象でございました。
視察の後に説明された方、消防署職員の方に、このスマホ、救急救命病院とはつながらないのかとお聞きしたわけですが、病院とはつながっていないと、こういうお話でございました。
救急現場から病院に搬送するまでの間にこの傷病者を待ち受けている救急病院に対して傷病者の様子を音声のみならず映像情報も送ることができれば、病院までの間に病院側も状況を把握し、そして準備を整え、救急救命に当たることがより円滑かつ迅速になるのではないかというふうに思いました。
この現状のLive119は民間のソフトでありますけれども、こうした、これに限りませんけれども、更に発展させて、救急車で搬送する傷病者の状況を待ち受ける救急救命センターに映像で送信し医師からの指示を仰いだり、あるいは手術の体制等、受け入れる病院側の準備にも資するようにしてはどうかと。
救急車で搬送中の映像の送信のため、今現状、救急車にも4Gのカメラが付いているのは承知しておりますけれども、5Gなどを活用した新たな技術の開発また実装が必要ではないかと思いますが、現状及び対策について消防庁にお聞きをします。
○政府参考人(五味裕一君) 消防庁において令和三年度に実施した5Gを活用した映像伝送の実証実験におきましては、救急隊と医療機関との間での映像伝送について音声のやり取りに鮮明な映像が加わることにより、医師が傷病者の状況を把握し指示を出しやすくなるなど、その有用性が確認されたところでございます。その一方で、現場活動において追加の作業が増えることに対する懸念の声も聞かれたところでございます。
5Gの普及が進む中、実際に救急隊と医療機関が連携してリアルタイムに傷病者の映像やバイタルサインを共有する取組も進んでおりまして、消防庁といたしましては、現場の救急隊の声もよく伺いながら、地域の状況に応じた優良事例の横展開を進めてまいります。
○西田実仁君 この指令センターでは、災害時のSNS上での情報も活用するというお話でした。しかし、今回の能登半島地震でも指摘されておりますように、災害時のSNS上には偽情報や誤情報も少なくないということが知られております。
今後、SNS上の災害情報等を扱う場合に、どうこうした偽・誤情報を見抜いていくのか、その対策について最後にお聞きして、終わりたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 消防指令センターでは、一一九番通報を基本に出動指令を行っておりますけれども、通報受付後、SNS上の情報を確認し災害の実態把握に活用している消防本部があるというふうに承知をしております。SNS上の情報には偽・誤情報も含まれる可能性があり、これにより不要な災害対応につながったり、真に必要な消防活動ができなくなるおそれがございまして、偽・誤情報対策は重要な課題であるというふうに認識をしております。
消防指令センターでSNS上の情報を活用している消防本部の中には、偽・誤情報への対策としてAIを活用した偽・誤情報を排除するソフトを活用している例もあるとお聞きをしておりまして、そのような例も含め先進事例を把握し、全国の消防本部に周知し、横展開を図ることなどを通じて適切な消防活動につながるようにしてまいりたいと考えております。
○西田実仁君 終わります。